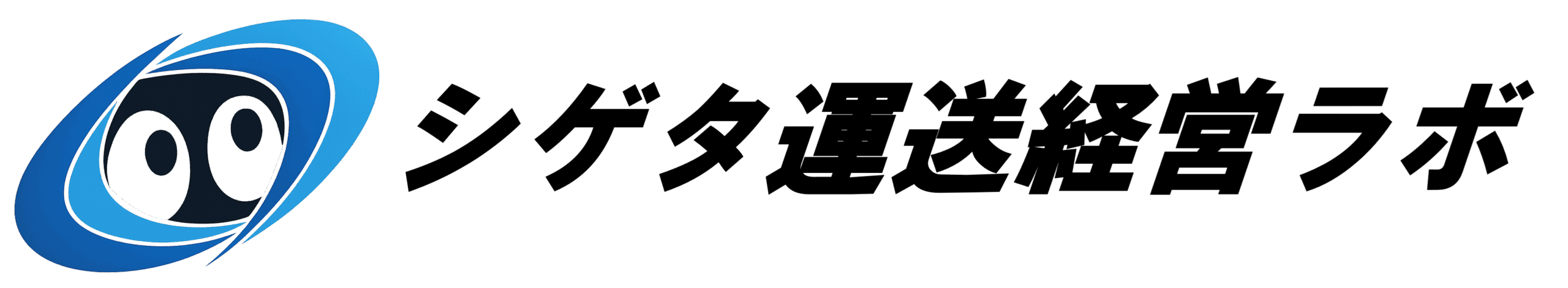パンデミック以降、物流業界には「ニューノーマル」とも呼ばれる新たな潮流が訪れています。物量の不安定化、人手不足、燃料費の高騰など、課題は山積み。その中で利益を出し続けるには、従来のやり方に固執するのではなく、抜本的な見直しが必要です。
今回は、物流コストを削減しつつ、サービス品質を維持・向上させるための「本質的な5つの改善方法」をご紹介します。
1. 過剰サービスの廃止 ~「お客様のため」が会社を苦しめる~
多くの企業が「顧客第一」を掲げています。そのこと自体は素晴らしく何も問題が無いように思えますが、本当にそうでしょうか。顧客第一が過剰なサービスに繋がってはいないでしょうか?
例えば、少量でも即配する。毎日複数回の集荷・納品など、本来であれば追加料金を請求すべき内容を「当たり前」として提供しているケースが見受けられます。
解決策:
- サービスの棚卸しを行い、コストと利益を見える化
- 「特急」「早朝」「夜間」「休日」などは、明確にオプション料金を設定
- 顧客との契約内容を見直し、標準サービスとの線引きを明確に
- 本当に顧客にとって付加価値の高いサービスならば有料で提供する
2. スポット運送の活用 ~繁忙期・閑散期に合わせた柔軟な運用~
固定契約による定期便だけでなく、スポット運送を活用することで、必要な時に必要なだけの配送が可能になります。
特に繁忙期の人手不足や車両不足を補うには、スポット運送は非常に有効。逆に閑散期にはコストをかけず、無駄な固定費を削減できます。
ポイント:
- 運送会社を開拓したり配送マッチングプラットフォームやクラウド運送サービスを活用する
- 提携運送会社のネットワークを構築しておく
- 社内業務と委託業務の役割を明確に分担する
3. 倉庫と配送の分離戦略 ~物流全体を俯瞰する~
「倉庫業務」と「配送業務」を明確に分離し、各業務の効率化を図ることも大きなコスト削減につながります。
特に、自社配送にこだわるがゆえに、非効率な運行ルートが常態化しているケースも。
逆に、地域密着の協力会社に配送を任せ、自社は在庫管理や受注処理に専念する体制に切り替える企業も増えています。
対策例:
- サードパーティロジスティクス(3PL)への委託
- 倉庫の拠点見直し(都市近郊への移転など)
- 小規模多拠点戦略の検討
4. テクノロジーによる業務効率化 ~アナログ脱却のススメ~
物流関係は、まだまだアナログな業務が多いのが現実です。
紙の伝票、電話やFAXでの受発注、Excelでの配送管理…。これらを見直すことで、ミス削減や時間短縮、ひいては人件費の削減にもつながります。自社でのDX化が無理な場合は既にDXに取り組んでいる運送会社に委託するのも一つの手です。
具体的な改善例:
- 配送管理システムの導入(運送業・自社運送部門)
- デジタル伝票(電子受領書や電子サイン)の活用
- バース管理システムの導入(倉庫業・自社倉庫)
5. 配送ルートと積載率の見直し ~“走り損”をゼロにする~
車両1台あたりの積載率を上げ、走行距離を短縮できれば、燃料費・人件費ともに削減可能です。
そのためには、ルートの最適化や積載状況の可視化がカギとなります。
施策としては:
- AIによるルート最適化ツールの導入
- 積み合わせ配送(混載便)の検討
- 帰り便(リバース物流)の活用
- 非採算ルートの見直しや、別途料金化
おわりに:コスト最適化は「我慢」ではなく「工夫」
物流コストの最適化は、単なるコストカットではありません。
「効率化」と「無駄の排除」を通じて、収益性と働きやすさの両立を目指すものです。
ニューノーマル時代においては、柔軟で持続可能な物流体制こそが企業の競争力を左右します。
まずは自社の物流業務を棚卸しし、小さな一歩から始めてみてはいかがでしょうか?